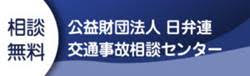三住 忍
- 2007年2月7日、法制審議会は、法務大臣に対して、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための法整備に関する要綱(骨子)」を提出した。
この答申は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強姦の罪,業務上過失致死傷等の罪、逮捕及び監禁の罪並びに略取、誘拐及び人身売買の罪等について、参加を申し出た被害者や遺族(以下「犯罪被害者等」という)に対し、「被害者参加人」という法的地位を付与し、公判への出席、情状に関する事項についての証人に対する尋問、自ら被告人に対して行う質問、証拠調べが終わった後における弁論としての意見陳述を認める被害者参加制度を創設することを求めている。
- しかし、この被害者参加制度は、犯罪被害者等について、「事件の当事者」から、「被害者参加人」という訴訟当事者又はそれに準ずる地位を容認するものであり、刑事訴訟の構造を根底から変えるものである。
起訴状に被害者として記載された者が真に被害者か否かは、刑事裁判の判決において初めて判断されるものである。
とりわけ、無罪を主張して、被害の有無それ自体を争う場合に、起訴状に記載された被害者を刑事訴訟に参加させて訴訟活動に参加させることは、無罪の推定の原則や予断排除の原則に抵触すると言わざるを得ない
- 近代刑事司法は私的復讐を公的なものに昇華させ、被告人は国家が処罰することにより、被害者は加害者からの再復讐から守られ、被害者と加害者との報復の連鎖を防ぎ、もって社会秩序の維持を図ろうとしている。
ところが、犯罪被害者等が刑事法廷で被告人と直接対峙すると、被告人に対する犯罪被害者等の言動が被告人の反発を招きかねず、また、被告人の中には、犯罪被害者等の訴訟活動によって自分が有罪とされ、あるいは重く処罰されたと考えて、逆恨みや報復感情を抱く可能性がないとは言えない。
このように犯罪被害者等が被告人と刑事法廷で直接対峙することは、近代刑事司法が断ち切ろうとした報復の連鎖を復活させることになりかねない。
- 被告人は、無罪推定の原則により、刑事法廷において、予断と偏見をできる限り排除して、自由に供述することができなければならない。
しかし、犯罪被害者等が、常時、被告人と直接対峙する形で刑事法廷に出廷することになれば、被告人には大きな心理的圧力がかかり、自由に弁解や反論をすることができなくなることが予想される。
- 刑事訴訟は、客観的な証拠により犯罪事実の存否や量刑が決められるが、犯罪被害者等は必ずしも全ての証拠を把握しているわけではなく、検察官とは情報量や立場が異なっており、証拠に基づく訴訟活動を期待すること自体に無理がある。
また、裁判員制度の下においては、犯罪被害者等の主張や陳述、応報感情に基づく弁論としての意見陳述が刑事法廷でなされることにより、初めて刑事法廷に臨む市民である裁判員が戸惑い、冷静な判断をすることができなくなるおそれがある。
- 犯罪被害者等の要望に応えるためには、まず、検察官と十分にコミュニケーションを図り、犯罪被害者等への情報提供や検察官の訴訟活動について意見を述べる機会を確保できる制度を創設すべきである。
また、十分な法的知識を持たず、捜査機関などによる二次被害に苦しめられる危険性に晒されている犯罪被害者等に対して、公費による弁護士支援制度を導入すべきである。
- 第166通常国会には、被害者参加制度の創設を含む刑事訴訟法改正案が上程されることが予定されているが、奈良弁護士会は、被害者参加制度の導入に反対し、国会における慎重な審議を求めるものである。
 奈良弁護士会
奈良弁護士会